目次
1. 日本政府と業界の基本戦略:「マルチパスウェイ」
経済産業省が提唱するのは、EVのみではなく「ハイブリッド(HEV)・プラグインハイブリッド(PHEV)・EV・燃料電池車(FCEV)」と多様な選択肢を持つ戦略(マルチパスウェイ)です。2035年にEV比率20%超を目指し、バッテリー・資源確保・政策連携を推進中です 。
この戦略は、制度とインフラの整備が不均衡な地域でも柔軟に対応できる「得意技」で、日本企業はそこを活かす方向へ進んでいます。
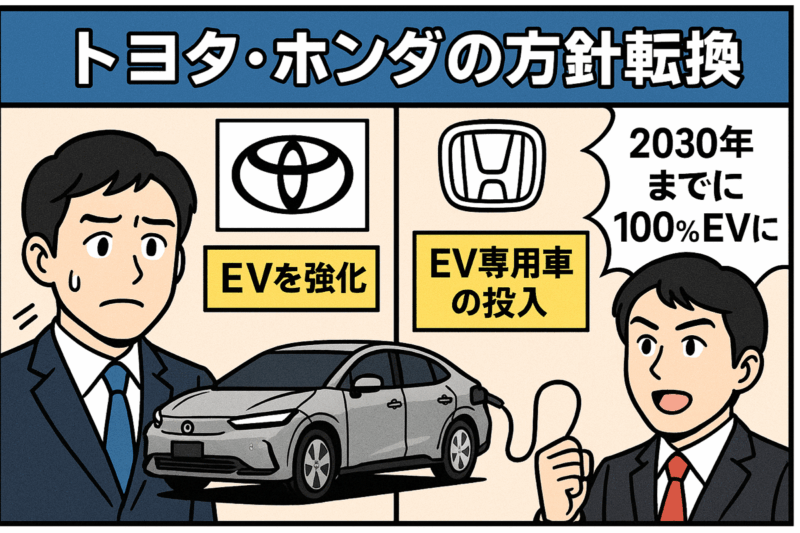
2. トヨタの「じわじわEVシフト」と全固体電池開発
✅ トヨタの戦略
- EVモデル拡充 2027年までにEVを15機種、年間生産100万台体制へ。主力EVとして北米や欧州向けに拠点設置中 ()。
- 多彩な電動化 EVだけでなくHEV、PHEV、FCEVも展開。2026年に電動車100万台、2030年にEV+FCVで350万台を目指す ()。
- 次世代電池の研究 2027年頃に全固体電池による航続1,000km級EV、製造量は2030年までに5兆円投資 。
- ソフトウェア&インフラ投資 車載OS「アリーン」開発、米リチウム電池工場拡張、工場は日本・北米・タイ・アルゼンチンでも展開 。
🔎 強みと懸念
- 強み:HEVの積み重ねによる市場基盤、新技術への基礎研究。
- 懸念:EVの即戦力性では後れ、全固体電池実用化が遅れれば競争で立ち遅れる恐れ。
3. ホンダの方針転換:EV投資の縮小とハイブリッド強化へ
🔄 舵を切る、ホンダ
- EV投資を30%圧縮 2030年にEV比率30%の目標を見直し、関連投資を69兆円→48兆円に削減 ()。
- HEVを主戦場に EV拡大が鈍化する中、2027年以降にHEVとソフトウェア強化へ集中。2040年ZEV完全実現の目標は継続 ()。
- 次世代EV「Honda 0」シリーズ ソニーとの合弁によるAfeela 1(2026年製造開始)、米オハイオ工場での導入準備中 。
- ** トヨタとの電池連携** 2025年からHYBRID用バッテリーを北米でトヨタ調達へ。米国の関税や政策変化に対応 ()。
🔎 強みと懸念
- 強み:短期的には市場に即応可能な戦略、HEVで収益確保。
- 懸念:EVの競争後退。特に米欧中でシェア争いに不利。
4. トヨタ vs ホンダの戦略比較
| 項目 | トヨタ | ホンダ |
|---|---|---|
| EV投資 | 積極拡大(15車種、100万台体制へ) | 一時縮小、HEV回帰(投資7兆円に圧縮) |
| HEV/PHEV | 両立重視、今後も拡充 | HEV中心に戦略変更 |
| 次世代電池 | 全固態電池に注力、2027年実用化目標 | 情報限定的だがHYBRID優先 |
| 連携関係 | BYDとEV技術、バッテリー自社化へ | トヨタからバッテリー調達+ソニー合弁EV |
5. 背後にある日本政府と外圧政策
- 政策環境 日本政府もEV普及・脱炭素を推進。ただしインフラ整備や電力基盤不足を考慮し、柔軟対応路線のEV比率目標を掲げ続けています ()。
- 国外要因 米国・中国などの関税・補助金政策影響。ホンダやトヨタは米国での電池調達や生産で供給安定化策へ ()。
6. 総まとめ:日本メーカーは「段階的EV移行派」
- トヨタ:EVへの本格シフトは“じわじわ”、HEVと次世代技術の複合戦略。全固体電池が鍵。
- ホンダ:短期はHEV重視へピボット。ただし将来EV・ZEV目標は維持。ソニー合弁EVなど次世代へ。
- 共通点:マルチパスウェイ路線。日本政府のEV普及方針、国外政策への柔軟対応が背景。
- 懸念:EV競争で遅れをとるロス、強力な中国勢(BYDなど)や米欧メーカーとのギャップ。政策次第では挽回可能。
✅ 結論
日本の自動車産業は、EV一辺倒ではなく、HEVやPHEV、全固体電池、EVと多角的に対応する「段階的移行モデル」を選びました。
トヨタもホンダも「EV化は進めるが、時期や手段を慎重に選ぶ」という姿勢を鮮明にしています。日本車が市場での存在感を維持するためには、「技術力」「政策調整」「グローバルパートナーシップ」の三点を揃えることが重要です。
コメント